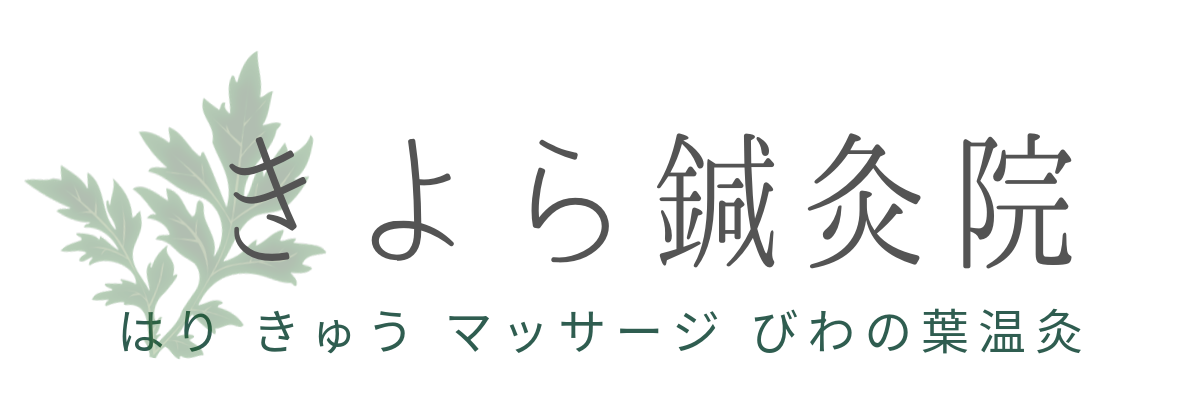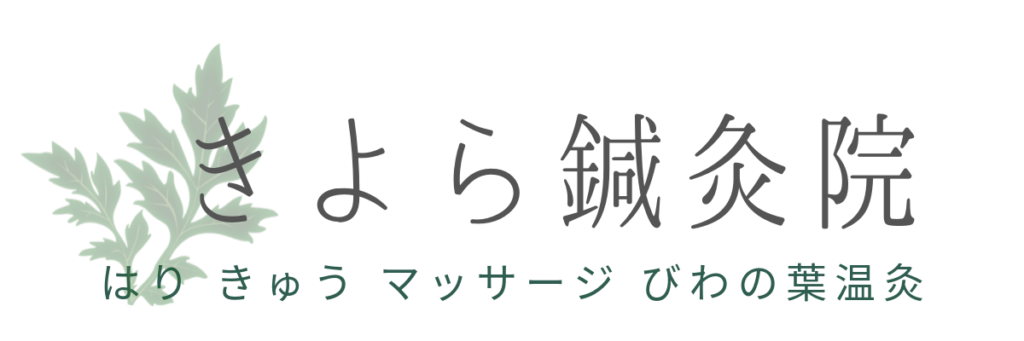お灸は中国から伝えられて
平安時代は貴族だけのものだった療法が
鎌倉時代には武士や庶民に浸透して
江戸時代にその文化のピークを迎えました。
前からずっと訪れてみたかった場所があります。それは、新潟県の佐藤竹右衛門商店のもぐさ工場です。学生でもないため、なかなか機会がなかったのですが、
今回2月13日、灸法臨床研究会さんの企画で見学に行くことができました。
良質のもぐさを作れるのは寒さが厳しい今の時期だけなので
作っている現場を見学できる期間は限られています。
幸運なことに現在JRで「旅キュンパス」なるキャンペーンをやっていて、新幹線に往復乗って1万円でした。

大宮から長野を過ぎたあたりで雪がちらつき始めます。




朝早かったので、名立駅で降りたお客は私だけ。
空が広く、雪と空のコントラストが美しい。

そして駅の真ん前に佐藤もぐささんの営業所が見えます!

現在流通している国産もぐさの7割がここのものだそうです。
もぐさは滋賀、富山、福井、石川などでも作られていましたが、
高温多湿で冬は雪が多く農閑期の労働力があった新潟が最終的にもぐさ製造の中心地となりました。

事務所の玄関マットに「SATOU MOGUSA」。

工場は事務所から少し離れた場所にあります。
前に降り立った瞬間から周囲に漂うもぐさ良い香りが周囲に満ちています。
なんと幸福な!

中はヨモギの粉が舞っているのでマスク必携ですが、
建物の脇の雪が、排ガスや泥で汚れているのではなく、
ヨモギ粉で黄土色になっているのが印象的です。

入り口に素敵な民芸品が、と思ったら破魔矢だそうです。

中国産と国産のヨモギの葉の香りの違いや
製造工程の注意点など、
現場に来なければわからなかった、知らなかったことを
たくさん六代目から教えていただきました。













もぐさは、よもぎの葉を真夏の一番暑い時期に収穫し、冬のこの時期に乾燥させてパリパリにします。
葉の緑の部分を取り除き、残った葉の裏のうぶ毛がもぐさになるのです。
200キロの葉からわずか1キロしか極上のもぐさは作れません。
ほとんど水分が抜けた乾いたヨモギの葉を臼や篩にかけていくと、どんどん緑色の部分が落ちて、
葉の裏のうぶ毛だけが残ります。
緑の部分が残っている度合いが高い色の濃いものほど燃焼温度が高く、
直接肌の上にすえない棒灸や灸頭鍼用のもぐさになります。
緑の部分が全部落ちて、完全にうぶ毛だけになったのが
肌に直接すえる最上級の「点灸用もぐさ」になります。


原料となるヨモギはアジア各地に生えていますが、
大ヨモギと普通のヨモギだけがもぐさになるヨモギで、
ヒメヨモギやカワラヨモギはもぐさには適しません。
もぐさを作るのに最も適した「うぶ毛の多い普通のヨモギ」は新潟県に自生しているものです。
(大ヨモギは温灸用にしているそうです)
そして間接的ではなく、直接お灸を肌の上にすえるのは日本独自の文化、
従って、点灸用のもぐさは日本製が世界一の品質ということになりますが、
極上のもぐさを作る技術はあるのに
調達する人材が高齢化して風前の灯で
材料のヨモギの葉が足りないという事態に直面しています。
もちろん今までのような、農閑期に
お小遣い稼ぎのような感覚で
雑草に紛れたよもぎの葉を集めてくださっていた農家の方々を当てにせず、
季節労働で新たな人を雇い
真夏の猛暑日に大量のヨモギの葉を刈ることができれば
原料不足は即解決するのですが
そのやり方で製造されたもぐさは
気軽に買えないような値段になるでしょう…
ヨモギの葉は現在お茶や肥料や健康食品の材料として人気があり、ひくて数多だそうですが
直接灸(点灸)をやらない鍼灸師が増えている今、ヨモギの未来は明るくても、
国産もぐさの未来は明るくありません。
(中国産でもある程度はできるそうですが
最良の熱感の極上もぐさは日本の限られた産地のヨモギからしか作れない)


「もぐさが以前ほど売れなくなった話」ではなくて
「原材料が足りなくてご新規の仕入れ希望はお断りしている状態」というお話でした。
工場見学は非常に楽しかったのですが、うーん…
今のような点灸文化は後世には伝えられないかも。

手に入るうちにたくさんお灸を楽しまねば!と決意をあらたにし、
直接灸用の純和灸極上もぐさを買いました。
これで10年は点灸用には困らない筈です。